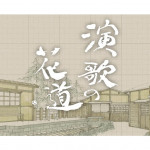【インタビュー】歌謡殿堂レジェンド〜成功への道〜 第一回:こまどり姉妹

思いが通じて運を開いていくんです
ーーコロムビアからレコードデビューするきっかけは何だったのでしょう?
敏子「当時、色んな子供がスターになった時代で、私達が流しの時から、自分がマネージャーになってひともうけしようと考えるお客さんがいてね。『僕はキングを知ってる』とか『テイチクを知ってる』とか『コロムビア知ってる』とか、いろんなレコード会社に連れてってくれるお客さんがいたんですよ」
栄子「いたんだけど、全然ダメなのよ」
敏子「歌ったんだけど、あの当時は、流しをしているっていうだけでダメだったのね。流しはね、今で言うヤクザのね、成れの果てみたいな仕事だってそういう感じに受け取られていたから。流しって言っただけで、世間から外れた世界に見られた。それに、飲んだお客さんと流しが取っ組み合いの喧嘩をしたり、事件起こしたり酷いこともあったのよ。流しの芸は上手なんだけどアル中になっちゃって、『酒飲ませてくれればお金はいいから』っていう芸人さんもいたりしてね。その当時はヒロポンが合法だったんですよ。流しには、ヒロポンを打ったりする人も多かったりして、底辺の仕事っていうイメージもあったのも事実です。歌どころじゃなくて、流ししてるだけでダメなの。コロムビアも2回位行って、ひばりちゃんを担当したディレクターも聴いてくれたし、他の人も聴いてくれたんですけど、でもダメだったの。それで、もうそういう所に行かないで自分達でお金貯めて、小さなお汁粉屋でも出しましょうっていうことで、歌手になるとかは、全然考えてなくなったのよ。その頃は、料亭などのお座敷に余興で呼ばれるようになっていて、ある日、コロムビアの社長さんが実業家の宴会みたいなところにいたんです。それで、余興が終わったら、『君、コロムビアにいらっしゃい』って声がかかりまして。その当時、神楽坂はん子さんがデビューして、『芸者ワルツ』とか『見ないで頂戴お月様』とか大ヒットしていた時代で、2代目を作ろうと思ったんでしょう。でも、もうその時、お姉さんは洋服のデザイナーになるつもりで、歌は18から20歳で辞めるつもりでいたから、歌は全然歌わないつもりでいたわけですよ」
栄子「やらないからって言ってたんだけど」
敏子「神田のほうにあるYWCAという学校に自分で行って、色んな勉強したりしてね。学校にも行けないで苦しんで芸をやってきた世界から足を洗いたいっていう気持ちがあったもんだから」
栄子「もう歌は歌わないと思っていたの」
敏子「洋服のデザイナーを目指して、免許も18歳で大型免許も取ってね。すごかったんですよ。私はお姉さんに『今日だけ付き合って』ってコロムビアに連れていったのがあるきっかけなんですよね」

ーー運命的ですね。
敏子「そしたら馬渕玄三さんっていう有名なディレクターさんが、私達ネッカチーフかぶって、浴衣みたいな恰好で、しょっぱい格好して行っているもんだから、『だれかそっちのほうで聴いてもらえ』って、鼻であしらわれてね(笑)。そしたら音が聴こえてきたの。『♪おはなちゃんおはなちゃん』っていう神戸一郎さんの新曲の音が。それで、音のする方へ行ってのぞいたら、小さなレッスン室で、1畳半か2畳位のピアノ1台置けるようなところで、神戸一郎さんが遠藤実先生からレッスンを受けていたの。その頃は、遠藤実先生の名前も知らないし、『ちょっと誰かに聴いてもらえ』って言われていたから、そーっとドアを開けて、遠藤先生と神戸一郎さんの後ろに椅子が2つ置いてあったから、そこに座ったんです。普通の素人だったらドアなんて開けられなわよね。でも、私達は、流しも余興もやって人馴れしているから、人の懐に入り込むのが特技でもあったのね。それで後ろに座って、神戸さんがお礼を言って出ていったら遠藤先生が振り返って『何で君たちそこいるの?』っていうから、『帽子かぶった人にね、歌聴いてもらえって言われたんです』っていったら、『じゃあ歌ってみな』って言われて、『何歌うの?』っていうから流しをしていた当時に歌っていた『裏町人生』(上原敏)とかひばりちゃんの『越後獅子の歌』とかを歌ったの」
栄子「妹が歌ったんですよ」
敏子「そしたら、先生がバッと振り向いて『君たち、それ誰に教わったの!?』って言うから、『教わりません。私達流しをやっていたんです』って正直に言ったのよ。流しの人達の歌い方って特別なのよ。抑揚があってね。酔っぱらったお客さんに聴かせるわけだから、普通の歌い方だと、酔客に『そんな歌出ていけ!』って言われるから、粘っこくね、情感のあるように、譜面通りじゃなくね、抑揚つけて渋く歌うから、その歌い方に先生がハッとしたわけね。遠藤先生が、『僕も流しを荻窪でやっていたんだよ』って話してくれたんですよ。『自分も流しをやって、そういう歌い方をやってきているから』って。そして、遠藤先生が『僕が馬渕君に言ってあげるから』っていうことで、馬渕さんに私達の歌を聴いてもらえることになったんです。運もその人の実力っていうことをよく言いますけど、コロムビアの社長さんに巡り合うのも運だしね。それで、声楽の学校出た人とか、特別のコンクールで優勝した人とか、皆が10人位歌を聴いてもらう日があるらしいんですよ。遠藤先生がそこに滑り込ませてくれたんです。でも、実は、東芝がレコード会社作る時に、私ひとりで第一号として、東芝から出ることになっていたんです。もう、収録間近で曲ももらってたんですよ。それで、占い師の藤田小女姫さんに、東芝がいいかコロムビアがいいかお訪ねしたら『東芝に行ったって、それっきりで目が出ない。コロムビアに行きなさい。それにはお姉さん連れて行きなさい』っていう話になっちゃたんですよ。それで、当日、私達の歌う番がきて、私が歌ったら、馬渕さんが「もういい」って言って、トイレに行っちゃったの。それでこっちも粘っこいから、別の『八丈恋唄』っていう民謡を、その場にいた遠藤先生に「先生、この歌まだ聴いてもらってないんです。この歌をぜひ聴いてもらいたいんです」って言ったら、普通一回ダメだって言われたらダメだよって言うじゃない。それを私達をよっぽどかわいそうだと思ったんでしょう。流しをしてきた女の子だしね。『僕から今頼んであげるから、ちょっと待ってな』って馬渕さんがトイレから戻ってきてから、『実はこの子達がこの歌を聴いてほしいって言うんだけどさあ』って先生が言って、馬渕さんだって渋い顔してたの“いいよ、どうでも”みたいな。それで遠藤先生の演奏で「八丈恋唄」を私が歌ったら、馬渕さんが『これだ!』って言ったのね。馬渕さんが遠藤先生に『このような曲を、君、この子達に書いてやってくれ』ってなっちゃった。私達の押していく、あきらめずに、これでもかこれでもかっていう思いが通じたのね。運を開いていくんですよ。それで今度ね、馬渕さんがお姉さんがいるのを見て、『お姉ちゃんも一緒に歌いなさい』ってなったのよ。お姉さんが『私は付き添いで来ているので歌いません』ってごねたら、『お姉ちゃんがダメならこっちもダメだよ』ってなったのよ。『頼むから付き合いで“うん”って言ってよ』ってね」
栄子「それで歌ったのよ」
敏子「お姉さんは、声が出なくて、高い音になると声がひっくり返っちゃうのね」
栄子「だから歌わなかったの」
敏子「自信もなくてね、歌はもう嫌だってなっていたのに、歌いなさいってなったからお姉さんがぶんむくれちゃってね。『お姉ちゃんね、出るところ下だけでいいから、出ないところ妹さんに歌わせるから、ちょっと合わせるだけでいいんだから、横に立っているだけでいいから』と言われてね(笑)。デビュー曲の『浅草姉妹』も『三味線姉妹』も上は全部私がやってるんです。途中にお姉さんが登場するわけですよ。そういうわけでステージでもお姉さんが三歩下がってね、『もう私は歌は嫌だ、一年経ったらやめる』なんて、騒いでいるわけです。だから私が前に出て、2人分声を出したりして、随分そういうことがあったの」
栄子「一年で辞めようと思ったの。しょうがないからね、一年だけやって。歌わなくていいだろうと思ったからさ」
敏子「そして一年位経って、今度レコードが売れ始めてきたでしょ。その時に辞めるっていうんだもの。そしたら親が『栄子、お願いだからもう一年、敏子に合わせて横に立っててあげてくれないか』って、両親が両手合わせてお願いしてさ。また一年過ぎて、本格的にギャラ上げてきたでしょ。その時また『辞める』って騒ぐしね。そして私が33歳でガンになって、命あるかないかで、一生歌っちゃいけないって先生に言われた時に、お姉さんの声が出てきたんですよ。取った仕事のキャンセルのお詫びまわりにまわっている間に、お姉さんの声がすごく出てきてね。性格が変わったの。それまで控えめで楽屋から出ないお姉さんがね、明るくなって私みたくしゃべるようになっちゃったのね。そしたらみんな、お姉さんを『妹さんでしょ?』っていうわけ。『私、姉の栄子です』って言ったら『お姉さんはそんな人じゃありません』ってそんなにしゃべったり歌ったりしないって言うの。面白いのよ。人生っていうのはね。それから積極的に私を支えてくれる立場になって」
栄子「それから今だにね、何十年もやれるようになったのよ」
ーーそれはすごいことですね。ドキュメンタリー映画『こまどり姉妹がやって来る ヤァ!ヤァ!ヤァ!』(2009年公開)も拝見しまして、感動しました。
敏子「あれ、調子の悪い時に撮られてさ。私、足を痛めていてね。足、引きずって歩いていた。でも私もよくしゃべったなと思いましたよ(笑)。ラーメン食べてるシーンでの釧路の『霧笛の街』っていうのもいい歌でね、あの中に入ってる歌、レコードになっていない歌も入っているんですよ」
ーーそれは貴重な作品ですね。
敏子「フジテレビのディレクターに千秋与四夫さんって方がいてね。畠山みどりさんの旦那さんになった人なんですけど。その千秋さんが『ふたりぼっち』っていうゴールデン番組のテレビドラマをやってくれたんです。生まれた時から一つ一つの話に石本美由起先生と遠藤先生が新曲をテーマ曲として作ってくれたんです。あれ、30回くらい続いたんですけど、それ全部、歌は遠藤先生と石本先生でね。素晴らしい歌が残っているんですよ」
ーー毎回、毎回作られていたんですか?
敏子「そう。テーマ曲をね。だからすごい貴重で有難い。普通歌手の人がああいう映画を撮ってもらったり、そういうことってないじゃないですか。だから、何でこまどりはおぺちゃ(鼻が低い)なあんな顔して歌も上手くないのになんであんなふうに映画作ってもらったり、『爆報!THEフライデー』とか、テレビに出て食べたり飲んだり、出ているでしょ。歌手の人はうらやましいと思っていると思うのよ。この年でさ、81歳にもなってステーキを600グラムとか食べれるんですよ。それも不思議なんですけど」
栄子「普通、食べられなくなるんだけどね、80過ぎたらね」
ーー日活映画『浅草姉妹』にも1960年に出演されているんですね。
敏子「そうそう、日活映画とか東映映画とかみんな作ってくれました。あの当時はね。小暮実千代さんがお母さん役になってくれてね。千葉真一さんと『りんごっこ三味線』みたいなのを弾いて、映画だけは7本位出てるかな? 主役の映画は2、3本あるよね。昔は忙しい興業の間に撮るからね、もう、大変だったの。20日間とか興行があって、北海道を一ヶ月回ったりするわけでしょ。そうすると毎日移動して違う所に行くでしょ。だからもう一ヶ月過ぎて東京戻ってきて上野が近づいたら涙がこぼれたのね。もう、その頃は、東京っ子になっちゃっているから。北海道生まれなんだけど。やっと家に帰れるなって。やっぱり『住めば都』っていうね。東京に慣れると恐ろしいもんでね。故郷を思う気持ちはありますよ。でもみんないないし、風景もなにも変わっちゃってね」
ーー浅草のお店ですと当時のまま残っているところはあるのでしょうか?
敏子「ほとんどないですね」
栄子「食べ物屋さんも変わっちゃって」
敏子「寂しいよね。でも、60年70年したらみんなそうなるね」
栄子「私達はさ、そんなのね、悲しいとかじゃないから。当たり前だと思っているからさ」
敏子「もう変わるのが当たり前でね」
栄子「そうそう」
敏子「そういう中を生き抜いてきたし、色んな変化のある、時の変化に対応して生きてきたから。今もこの年でね、こういう帽子かぶって生きているんだから。昔だったら、想像もつかないんだけども」
ーーよくお似合いで素敵です。
栄子「若い時のこういうのも着るからね」
敏子「テレビっていうのは恐ろしいのよね。『爆報!THEフライデー』に出ていたら、この前、私、マクドナルドから表に出たとたんに、小さい小学生の女の子と中学生位の女の子が追っかけてきて、『こまどりさんでしょ?』って言うから『そうですよ』って言ったら『写真一緒に撮ってください』って言うんだもの。びっくりしちゃってさ」
栄子「テレビ見て若い子が、私達のことを知ったわけよ」
敏子「浅草の新仲見世を歩いているとね。おばさんたちが寄ってきて、『こまどりさんに会えた! 綺麗だわね』なんてきたもんね。81歳にもなって綺麗もなにもないじゃないね」
栄子「私達より10歳か20歳下だけど、上にみえちゃうわけ、そうなっちゃうのよね」
ーー現役で続けられているということも若さの秘訣なのかもしれませんね。
敏子「日本の女性って、子供出来たり孫ができたりすると、おばあちゃんって言われるとおばあちゃんのような色を着ないといけないかな。おばあちゃん言葉を使わないといけないかな、みたいな。そういうことに、左右されるんですよね。私は子供いないし独身だしね。孫もいないし。そういう楽しみはないんですけれどもね。人類は皆、産める人は産めばいいし、産めない人は無理に産まないほうがいいと思う。私も有名な占い師の方達と知り合いで観てもらったら、あなたは子供に縁がないから、産んだら子供で苦労するから、子供は産まないほうがいいと、その分の働いたお金を全部自分にかけなさいと、自分で楽しみなさいと。そういうあれで見ると、男の子一人産むと、大学入れないといけないとか、親が苦労して働いたお金を何千万もかけて、親孝行してもらえなかったら辛いじゃいの。私そういうお金全部、自分の食べたいもの食べて、買いたいもの買ったりして生きてきたから。そういう意味では幸せなんですよ。今、時代が変わって、お墓に誰誰と一緒に入らねばならぬ、とかっていう時代じゃなくなって、山に撒いてくれだの海に撒いてくれだのっていう時代になってきたじゃないの。そうすると、そういうとらわれ方しないで済むでしょ。お姉さんとも話してさ、無理矢理そんなかしこまったことやらなくていいと、あとの人達にもなにもお墓参りしないからどうのこうのっていうこともないしね。自然にまかせて、コトっと死ねばそれなりにね。それなりでいいんじゃないっていう感じでね。気楽に生きているから」